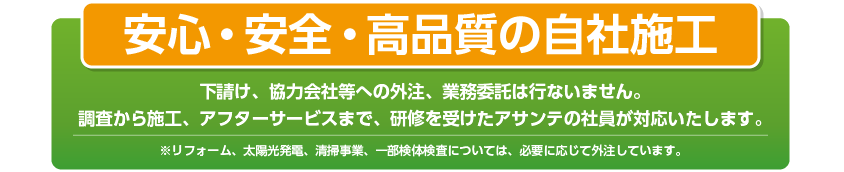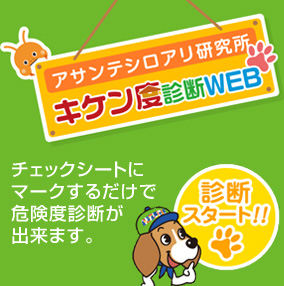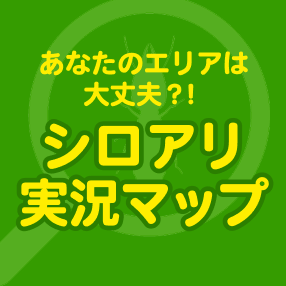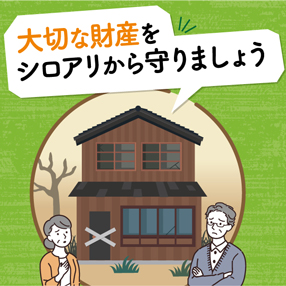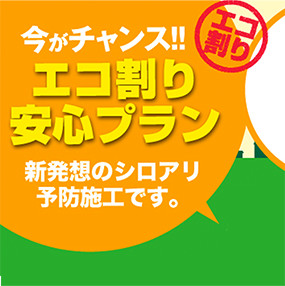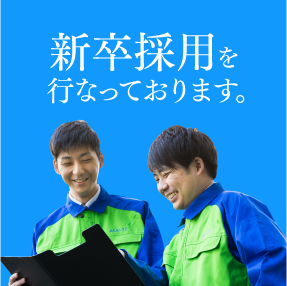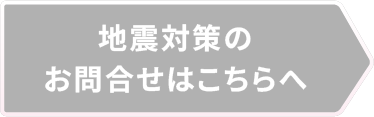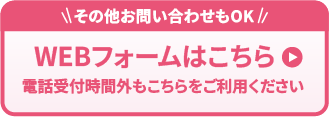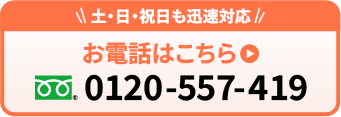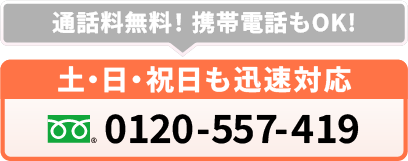ホーム > サービス > 地震対策 > プロに学ぶ!地震対策 > 戸建ての耐震性能|耐震基準や耐震等級、耐震性を高める方法とは?業者選びのポイントも解説
戸建ての耐震性能|
耐震基準や耐震等級、
耐震性を高める方法とは?
業者選びのポイントも解説

戸建てのマイホームをお持ちの方は、住宅の耐震性能がどうか、ご存知でしょうか。地震大国の日本では、建物の耐震性能はとても重要です。しかし、住宅の強度を高めるための具体的な方法がわからない、という方も少なくないでしょう。
そこで本記事では、戸建ての耐震性能の概要から補強方法、費用相場を解説します。戸建ての地震対策をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
木造住宅の補強とは
日本は地震が頻発しており、南海トラフや首都直下地震の発生が近づいているともいわれています。木造住宅の強度を上げるためにはさまざまな方法がありますが、どのような補強が必要か、適しているのかを判断するのは、専門家ではないと難しいといえます。
まずは、木造の戸建て住宅の補強にはどのようなものがあるか、耐震診断や耐震補強の基本を解説します。
耐震診断と耐震補強
地震による倒壊から人命を守るため、耐震改修による住宅の耐震性能の向上が推奨されています。まず現時点で住宅がどの程度の地震に耐えられるのか、どの箇所が弱いと考えられるかを調査することが必要です。この調査を耐震診断といいます。
耐震診断には専門家による診断だけでなく、一般の方でもセルフチェックできる「誰でもできる我が家の耐震診断」という診断方法があります。気になる方はチェックしてみましょう。
耐震改修による補強方法
耐震改修のためには、専門家による耐震診断や改修計画の立案が必要です。耐震診断で壁や柱の仕様や数、配置状況、劣化状況など複数のポイントがチェックされ、その結果をもとに、どのような改修を行えば地震に対して強くなるか計画が立案され、計画に沿って工事が行われます。
具体的な補強方法には、以下のようなものがあります。
耐力壁(地震などの力に抵抗する能力を持つ壁)の設置
筋交いの設置
金具による柱の接合部の補強
劣化した部材の補強や交換
屋根瓦等の軽量化
補強を検討する場合は、耐震診断や耐震改修工事を請け負ってくれる専門業者に依頼しましょう。
戸建ての耐震性能について
戸建ての耐震性能は、主に耐震基準と耐震等級の2つの指標で評価されます。ここでは、これらの指標と地震対策が必要な住宅の特徴を解説します。
旧耐震基準と新耐震基準、
2000年基準とは
耐震基準とは、建築基準法に基づいた、建物が地震に耐えられるための設計基準です。建物の耐震性を保証することを目的として設定されました。
耐震基準は段階的に強化されており、木造住宅では建築年月日でどの基準の時期に該当するかが判断できます。
| 適用開始の年度 | 耐震性能 | |
|---|---|---|
| 旧耐震基準 | 1981年5月31日まで | 震度5程度の地震で建物が倒壊しない |
| 新耐震基準 | 1981年6月1日から | 震度6強から7程度の地震でも倒壊しない |
| 2000年基準 | 2000年6月1日から | 木造住宅に関する細かな基準が義務化 |
参照: 「新耐震基準」から40年を振り返る|国立研究開発法人建築研究所
1981年6月と2000年6月の改正が節目となっています。
耐震等級とは
耐震等級とは、住宅性能表示制度に基づいて建物の耐震性能を3段階で評価する基準です。
耐震等級の基準と目安は以下となります。
| 耐震等級 | 耐震性能の基準 | 耐震性の目安 |
|---|---|---|
| 耐震等級1 | 建築基準法の最低限の耐震性能 |
大規模地震(震度6強〜7程度)でも倒壊を防ぐことを目指した基準。 耐震性を確保するための最低基準。 |
| 耐震等級2 | 耐震等級1の1.25倍の耐震性能 |
学校や病院など、避難場所となる公共施設に求められる基準。 大規模地震でも軽微な補修で対応できる耐震性能を持つ。 |
| 耐震等級3 | 耐震等級1の1.5倍の耐震性能 |
警察署や消防署など、災害時に重要な役割を担う建物に適用される基準。 大規模地震でも機能を維持する耐震性能が求められる。 |
参照: 新築住宅の住宅性能表示制度ガイド|一般社団法人住宅性能評価・表示協会
建築基準法で定められた法律上の基準である耐震基準に対して、耐震等級は建物の耐震性能をさらに細かく評価する指標である、という違いがあります。
耐震性能の見直しが必要な家の特徴
耐震性能の見直しが必要な家には、以下のような特徴があります。
築年数の古い木造家屋
柱などの劣化がみられる
柱と土台の接合部分が緩んでいる
壁が少なく開口部が大きい
重い屋根瓦を使用している
築年数が古い家は、旧耐震基準で建てられているかもしれません。老朽化による劣化も進んでいる可能性が考えられるため、早めの対策を検討しましょう。
耐震診断の重要性
大規模な地震災害から家族を守るためには、住宅の耐震性能が重要です。この耐震性能は、専門家による耐震診断で確認できます。
現行の耐震基準に適合しているか確認できる
基礎や柱の劣化を発見できる
耐震改修の具合的な方法がわかる
耐震診断については、こちらで詳しく解説しています。
木造住宅の耐震性能を高める方法
木造住宅の耐震性能を高めるには、以下のような方法があります。
壁に耐震パネルを増設する
壁内に筋交いを追加する
屋根の軽量化をする
柱や梁などの接合部を金物補強する
基礎コンクリートの補強
これらの補強工事を行うことで、建物の耐震性能を高められます。
耐震診断の結果をもとに具体的な耐震計画を立案します。
DIYだけで耐震性能を高めるのは難しいでしょう。
壁の筋交いや接合部の金物補強などは単に設置するだけに見えるかもしれませんが、耐震補強では建物全体のバランスが極めて重要です。
さらに、劣化が進んでいる箇所だけを補強しても、十分な耐震性能を得ることはできません。耐震診断の結果をもとに、建物全体のバランスを考慮した補強設計が必要です。
耐震性能を高めるためには、専門家に補強工事の設計から施工まで依頼することをおすすめします。
アサンテの地震対策工事
耐震工事では、耐震・制震・免震の観点で補強が考えられ、基礎や壁、屋根などに補強工事が施されます。これらの工事は大がかりになることも少なくなく、工期が長く費用がかさむこともあります。
例えばアサンテでは、法的な耐震基準を満たすまでは届かないものの、大がかりな工事を伴わず、費用を抑えられて、短い施工期間で済ませられる地震対策工事を行っています。
【金物補強による
アサンテの家屋補強システム】

金物補強の例
アサンテは、柱と梁、柱と土台といった接合部分を金物で補強し、倒れにくく抜けにくい柱へと補強することで倒壊を防ぐ補強工事も行なっています。
【アサンテの基礎補修】

基礎補修工事の様子
コンクリートのひび割れが生じることで鉄筋が外気に触れて酸化することがあります。酸化が進むと鉄筋が膨張し、その結果、ひび割れが進行して基礎の強度が落ちる悪循環となってしまいます。
そのため、基礎のひび割れは放置せずに補修を行うことが重要です。
アサンテは、コンクリート補修材を使用し、基礎部分の強度の維持と劣化を抑止する基礎補修工事を行っています。
床下と屋根裏のプロであるアサンテがしっかりとチェックし、日常生活や外装・内装への影響を抑えた自社施工を実施します。費用を抑えながら、工期が短いのも特徴です。
アサンテが行っているこれらの地震対策は大がかりな工事を伴わないため、工期が短く費用を抑えることができる点が特徴です。
無料の調査を行い、お見積りを見てじっくり検討していただける体制を整えていますので、既存住宅の耐震性が気になる方は、ぜひご相談ください。
耐震補強の種類と費用目安

一般財団法人日本建築防災協会の調査によると、耐震補強工事にかけた費用の中央値は以下のとおりです。
木造住宅(2階建て):186万円
木造住宅(平屋建て):140万円
一般財団法人 日本建築防災協会「-耐震改修ってどのくらいかかるの?-耐震改修工事費の目安」
補強の種類や築年数によって費用は変動します。以下で具体的に解説します。
耐震補強方法別の費用相場
耐震補強工事の費用は、補強する箇所と工法によって変わります。
【補強箇所別の費用相場】
| 補強箇所 | 費用目安 | 施工内容 |
|---|---|---|
| 基礎 | 50〜150万円 | 基礎のひび割れ補修や金物で補強する工事 |
| 壁 | 20〜80万円 | 耐久壁の設置、筋交いを補強する工事 |
| 屋根 | 50〜200万円 | 重い瓦屋根を軽量な素材に変更する工事 |
【補強工法別の費用相場】
| 工法 | 費用目安 | 施工内容 |
|---|---|---|
| 耐震補強 | 150〜200万円 | 壁や基礎の接合部を補強し、建物自体の強度を高める工法 |
| 制震補強 | 50〜300万円 | 制震ダンパーを取り付け、揺れを吸収、抑制する工法 |
| 免震補強 | 250〜300万円 | 建物と地盤を切り離し、揺れを直接伝えないようにする工法で、新築の際に行うのが一般的 |
※2025年2月時点のインターネット等の公開情報をもとにしています
既存住宅の補強工事は、耐震補強と制震補強が一般的です。免震補強は住宅の持ち上げや解体が必要となるため、現実的ではありません。
補強する箇所や範囲によって費用は大きく変動するため、耐震診断をもとに施工内容を検討しましょう。
築年数や耐震基準による費用の違い
築年数ごとの耐震工事費用の相場は、以下のとおりです。
| 建物の築年数 | 耐震工事の費用相場 |
|---|---|
| 築20年以下 | 約50〜100万円 |
| 築21〜30年以下 | 約130〜150万円 |
| 築31〜40年以下 | 約170〜200万円 |
| 築40年以上 | 約190〜250万円 |
参照: 木造住宅耐震診断調査データ/日本木造住宅耐震補強事業者協同組合
築年数が古くなるほど、耐震補強の費用は高額になりがちです。特に旧耐震基準で建築された住宅は、補強箇所が多くなるため費用がさらに高くなる可能性があります。
費用を抑えて地震対策を行う方法
地震対策の費用を抑えるには、国や自治体の補助金制度を活用するという方法があります。工事を検討する際には複数の業者から相見積もりを取り、見積もり内容を比較検討することも重要なポイントです。相見積もりを取ることで、費用の適正価格も把握しやすくなります。
費用が高額になってしまう場合は、優先度の高い工事から施工することもできます。ただし、工事を数回に分けることで逆に費用がかさんでしまうこともあるため、しっかり検討することが大切です。
住宅の耐震性能と老朽化の状況に応じて、適切な方法を選択しましょう。
耐震補強工事を行う際の業者選びのポイント
業者に耐震補強工事を依頼する際は、以下のポイントを抑えておくと業者選びで失敗しにくくなります。
耐震工事の豊富な経験がある業者
資格を持つ専門家が在籍している
工事計画や施工内容が明確でわかりやすい
アフターフォローの保証内容を確認する
実際の施工業者の確認も大切です。下請けに外注しているのではなく、自社施工を行う業者の方が施工品質が安定し、問い合わせ先も明確なのでおすすめです。
これらのポイントを確認しながら、複数の業者を比較して選ぶようにしましょう。
まとめ
本記事では、戸建ての耐震性能の概要、耐震性能を高めるための方法と費用相場を解説しました。
大規模な地震災害が想定される日本において、補強工事の検討は住まいと家族を守るために重要です。診断を受けて、自宅に合う補強工事を検討してみてください。
アサンテでは、費用を抑えた短期施工が特徴の地震対策工事を行っています。
1. 信頼と実績の東証プライム上場企業
2. 床下と屋根裏のプロがしっかりと点検
3. 外注工事なしの自社施工
4. 家屋を解体しないため日常生活への影響が少ない
5. 工期が短く費用を抑えることが可能
6. 無料の調査とお見積りでじっくり検討できる
大切な家を守るために、定期的に耐震性を点検し、必要に応じて適切な補修工事を行いましょう。耐震補強を検討中の方は、アサンテの家屋補強システムをぜひご検討ください。